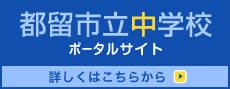令和6年度 ニュース
宝小ニュース
長さをはかる
2025-02-04
NEW
2年生の教室では、握ったこぶしの小指と人差し指の間の長さをものさしではかっていました。昔からものの長さをはかるときに、人々は体の一部の長さを単位としていました。握りこぶしの幅は「つか」と言いますね。2年生は自分の「つか」の長さをはかっていたのです。長さを比べたり覚えたり見当をつけたりするときに便利ですね。自分のつかが11cmだったら、「つか」2つ分で約22cmということがわかりますね。「つか」3つと半分だったとしたら・・だいたい分かります。もっと長いものを図るとき例えば黒板の横の長さだとしたら、「つか」だと手間と時間がかかります。もう少し長いものが単位となるほうが便利です。そこで両手を左右に広げた中指から中指までの長さ「ひろ」という単位があることを2年生は知りました。自分の「ひろ」の長さが分かると「ひろ」がいくつ分ということで、長いものもだいたいどれくらいの長坂分かります。そこで、2年生のみなさんは、友達と協力して自分の「ひろ」の長さを測りました。自分の「ひろ」の長さをはかれば、「ひろ」いくつ分ということで長い長さもはかれます。最初は30cmのものさしではかったのですが、ものさしを一つ分二つ分とやっていくと誤差がおおきくなるのです。そこで、長めの紙テープを使ってメジャーのようにはかってみました。紙テープですから目盛りはありません。考えて工夫してみることも大切な学習です。見ていると、30cmのものさしをつかって30cmごとの目盛りを紙テープにつけていたみなさんがいました。さらに様子を見ていると、友達の「ひろ」をはかって、30cmの目盛り4つぶんでした。ここまでで120cmということが分かりました。その先だけものさしをつかってはかってみたら3cmでした。だから123cmであることが分かりました。このグループは自分たちが工夫してはかった過程を発表してくれました。そのほかに、目盛りを1cmや10cmというふうにつけてはかっていたグループもありました。子供たちのアイデアや工夫は素晴らしいです。授業の最後に今日の学習のまとめを書いているときの2年生は、とても真剣で集中していました。